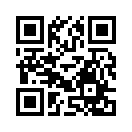2006年05月09日
今日は何の日?(5/8) 回答編
5/8が「ゴーヤの日」というのは日本全国で一体どれ位の人が知って居たでしょうかね?
また、GW沖縄に旅行に来た人でその日の宣伝を目にした人はどれ位居たのかな?
前回の記事に対するコメントが無かったので日本全国にどれ位「ゴーヤの日」が定着しているかはうかがい知ることは出来ませんが、
5/8 も過ぎた事だし 今回は「ゴーヤの日」について詳細を書いていきましょう。

(1997年から県をあげて宣伝しだしたこの日が2006年を迎えてどれ位日本全国に浸透したかは全国民調査をした機関がないのでわかりませんが、実際のところはどうなんでしょうかね?
日本全国からのコメントお待ちしております
 。
。ここを見る人は沖縄に興味のある人ばかりだから100%の人が知っているかな?

 )
)《 五月八日はゴーヤーの日 》
1997年の5月8日に 5/8をゴーヤの日にしようという
県と経済連をあげての戦略(沖縄県産品としてのゴーヤのアピール)がスタートしました。
ちゅらさんの沖縄ブームや田舎暮らしブームも重なって沖縄のゴーヤーの名前は全国に知れ渡るようになりました。
ゴーヤの知名度全国区化計画にとって、
特に「ちゅらさん」の影響は大きいでしょう!!
あのゴーヤーマンが何気にゴーヤーの知名度を上げるのにとっても重要なキーマンであったのです。(いまだに沖縄の御土産やではゴーヤーマンを見かける事ができます。)
かく言う私もちゅらさんは全話見なくともゴーヤーマンキーホルダーはしっかり購入しました。
また、
沖縄ブームに追加して沖縄の食品(ゴーヤ)を分析しアピール・商品化しだす会社が増えてきたのも知名度を上げた要因の一つです。
東京などの市街地に「沖縄料理の店」も多く出来沖縄以外で沖縄料理を食べる機械・場所が増えたのも要因の一つにあげられます。
1997の当時の沖縄の新聞にはこう有ります。
**********************
「ゴーヤの日/沖縄が誇る健康食/全国の食卓を飾ろう/那覇と東京で宣言大会 」
五月八日を「ゴーヤーの日」に。
県内野菜を代表するゴーヤー(苦ウリ)の消費と生産の拡大を目的に、県農水産物販売促進協議会が中心となり、八日、沖縄と東京で「ゴーヤーの日」宣言大会が行われた。
また、県内各地でもゴーヤーに関するイベントなどが開かれ、長寿食、健康食として県産品ゴーヤーを大いにPRした。
那覇市内の沖縄ハーバービューホテルで行われた宣言大会には、約二百五十人が参加。
当銘由孝県経済連常務が「ゴーヤーは長寿県沖縄を象徴する健康野菜。長寿野菜として全国の食卓を彩ることを祈念してゴーヤーの日を宣言する」と宣言した。
*************************
また、
その当時の県経済連発表によると、
1995年度は 5700トン(実績)、
1997年度は 11200トン(見込)、
2000年度は 15700トン(見込)との予測であった。
しかし、
今年度の実績を見てみると。
実際は、2000年度は6000トンであり、大分当時の予想とズレる結果となっていることがわかります!!三倍近くの予想とのズレ。
(この辺の楽観的な予測の出し方はいかにもお役所仕事らしいですねっ )
)
これを
当時の予測の甘さ
というか
今までの県制の失敗の積み重ねの結果
というかは、皆さんの判断に任せますが・・・。
年間約16000トンもの生産を見込むには、
どれ位の畑が必要であり、
どれ位の消費者が見込まれないといけないか、
どんな販売経路。流通経路を整備しないといけないか、
県としてどんなアピールを日本全国にしていかないといけないか、
は沖縄の経済連のTOPは解っているのでしょうか?
県制のチグハグさが見えます。
(上記は、「今までは・・・。」であり、現在は少し連携がとれトータル的に事業が展開するようになりいい方向に向かっていると思います。)
本来ならこの予想と現実の差がなんであり、どうすればよかったのかまで調査・結果をマトメ失敗点を学習出来れば、沖縄経済の伸びに繋がると思うのですがそういうのは現状沖縄に無いというのが残念なところです。
(いかに予算を使い切るかのその場対応の事業が多いい。。。)
また、
逆に考えるとそのようなりサーチ会社やコンサルタント会社のニーズが沖縄にはあると言えよう。
しかし、
私もフリーのライターとして記事を書く以外に企業のコンサルタントもやっているのですが(ホンの少しですが )、やっぱり沖縄の血族社会の壁は厚いです。
)、やっぱり沖縄の血族社会の壁は厚いです。
(特に沖縄の経済連のTOPは沖縄がどう発展すればよいとかでなく、いかに自分の特になるか・言う事を聞くかが重要であり。。。(←これは沖縄に限った事ではありませんでしたねっ )辛口に思った事をズバズバいう私には仕事は出ないし、更には排除しようという見えない力が働いている・・・というのが実際でしょうか(笑)
)辛口に思った事をズバズバいう私には仕事は出ないし、更には排除しようという見えない力が働いている・・・というのが実際でしょうか(笑)

 )
)